
地域伝統織物
三河木綿について
Mikawamomen History
三河木綿の歴史
日本ではじめてワタが伝来されたとされる三河国
西暦799年(延暦18年・平安時代の初め頃)桓武天皇の頃の記「類聚国史」や「日本後記」によれば、崑崙人(インド人と言われている)が愛知県幡豆郡福地村(現在の西尾市)に綿種を持って漂着しました。
これが日本の綿(ワタ)の伝来と言われています。
国産木綿がはじめて文献にみえるのは、永正7年(1510年)で「永正年中記」に年貢180文の分として「三川木綿」をとったと記されており、当時、税として三河産の木綿を徴収していたことがうかがえます。

五百年以上の歴史がある綿織物業の産地
最初に綿業が根を下した土地は三河であり、永正年間(1504~1520年)すでに綿織物業がおこり、天文年間(1532~1554年)以降、木綿商人は積極的に販路を京都方面に求めたと言われています。
永禄年間(室町末期)に三河を平定した家康は地域の木綿業を保護し、その後江戸時代になると農家の副業として三河地方で展開されるようになりました。

三河地方は綿業が他の地方に先駆けて発展し、 さらに西洋の技術を取り入れ、明治時代には「三河木綿」「三河縞」というブランド名で全国に知れ渡りました。
また、木綿専業だった愛知の糸の技は、明治時代を迎え多彩な素材(羊毛・レーヨンなど)を扱うようになり、愛知は国内屈指の繊維産地となったのです。
現在では三河地方での綿の栽培は衰退してしまったものの、繊維関連の企業や工場、機屋はまだまだ多く、地域伝統産業として今日まで受け継がれています。
Mikawamomen’s features
三河木綿の特徴
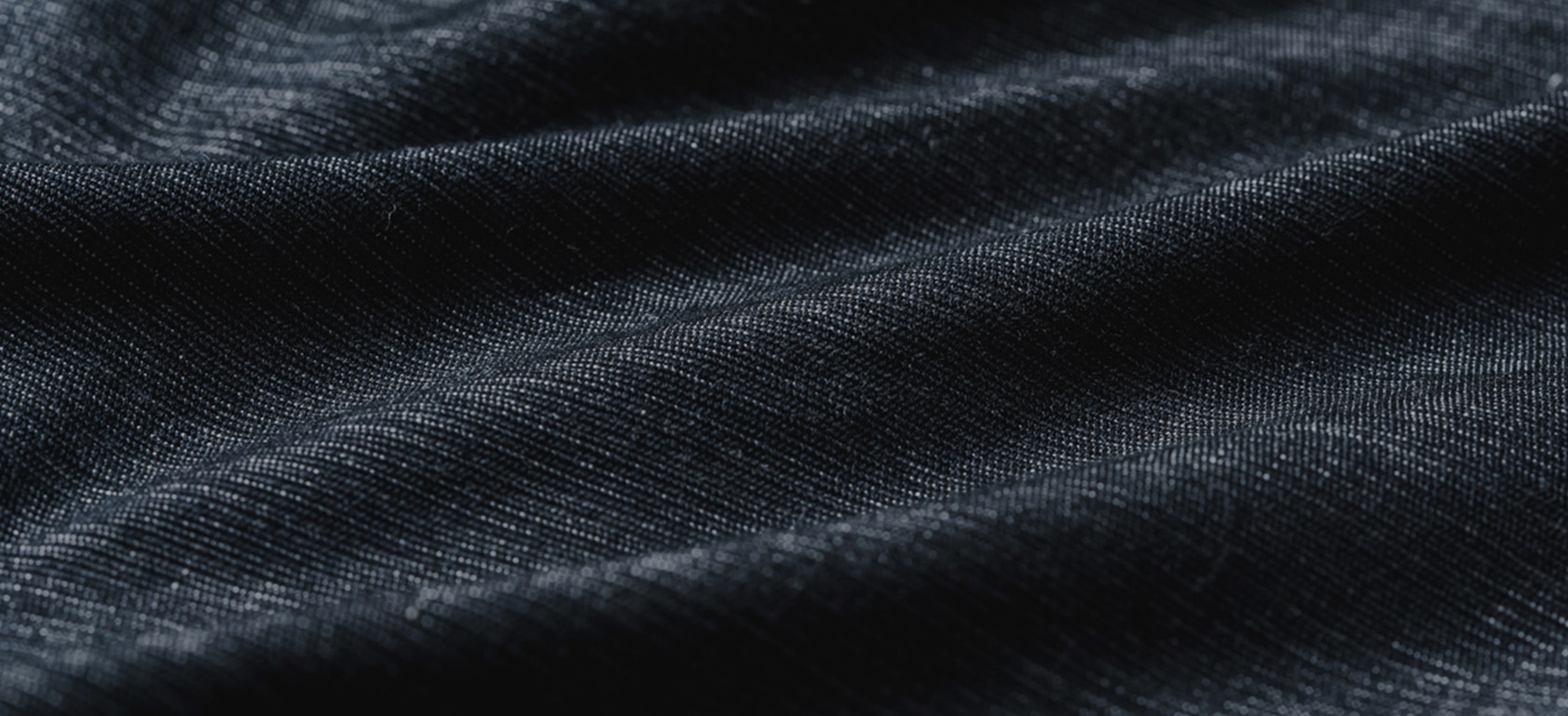
三河木綿とは、三河地方で織られた綿織物の総称です。
地域団体商標に登録されており、認定基準を満たした綿織物が三河木綿と呼ばれ親しまれています。
三河地方で古くから発展してきたジャガード織機は、厚地で丈夫な木綿を織ることを得意とします。
そのため、他の産地と比べ丈夫で耐久性のある木綿が多く、もともと農家の衣服である野良着としても好まれていました。
また、「三河縞」というはっきりとした縦縞模様も、三河木綿の特徴の1つとして愛されています。

弊社ではその三河木綿を使用し、婦人服・紳士服をはじめ、さまざまな衣料品・生活用品を提案しています。
地域の工場や機屋と協力し、弊社オリジナルの三河木綿も開発。
着るほどに馴染む、野良着としても優秀な三河木綿。
この地域で発展してきた産業をこれからも繋いでいくために、これからも地域と共に歩んでゆきたいと考えています。